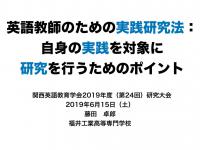今年度の口頭発表の中で、HPに掲載されたものについてお知らせします。
(1)中部地区英語教育学会第50回記念愛知大会にて、永倉由里先生(常葉大学)と南侑樹先生(神戸市立工業高等専門学校)と共同で「実践共有コミュニティに関する調査から読み取れる英語教育の現状とニーズ」という題目で発表させていただきます。
https://www.celes.info/aichi2020/
(2)外国語教育メディア学会(LET)第60回全国研究大会にて「英語教師のための実践研究法ワークショップ」というタイトルでワークショップを担当させていただきます。貴重な機会をいただき深く感謝いたします。実践研究について具体例やクイズを用いながら理解を深めていただけるように努めたいと思います。
https://www.j-let.org/let2021/
(3)全国高等専門学校英語教育学会第44回研究大会にて、南侑樹先生(神戸市立工業高等専門学校)・河合創先生(福井市大東中学校)・宮﨑直哉先生(掛川市立桜が丘中学校)と共同で「ビデオ会議ツールを活用したオンライン読書会の効果と課題」という題目で発表させていただきます。
http://cocet.org/conference.html
口頭発表は1年ぶりでちょっと緊張しますが、皆様にお会いできるのを楽しみにしています。